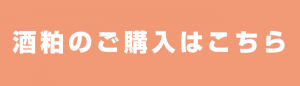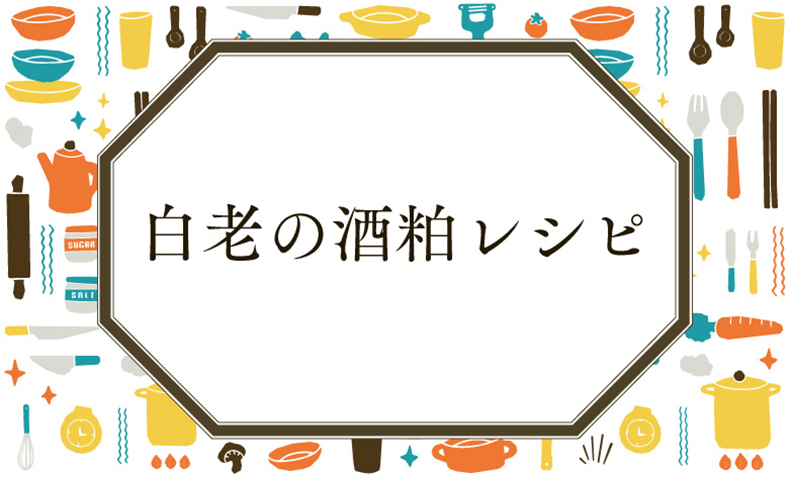
白老 蔵元の酒粕レシピ
〜純米粕編〜
酒粕は、冬に新酒を搾ってできる副産物です。
まだアルコール分が8%ほど残っていますが、タンパク質や各種のビタミンが含まれ、大変栄養価の高い食品です。
手軽にあま酒を作ることが多いのですが、それ以外にもいろいろご利用いただけます。
蔵元ならではの食べ方もありますので、ぜひご参考いただき、酵母が生きた発酵食品で健康な食生活をお楽しみくださいね。
☆寒い時期の定番、身体も心もぽっかぽか!☆

【材料:3〜4杯分】
純米酒粕 100g
砂糖 大さじ3
水 500cc
塩 ひとつまみ
しょうがすりおろしまたは搾り汁 お好みで
※砂糖は粕と同量〜70%くらいが目安です
【作り方】
(1)酒粕を細かくちぎって、一晩水につけます。
(2)(1)の酒粕をよく溶かします。
(ミキサーかすり鉢でのばすとなめらかになります)
好みの量の水で溶き、よく煮立たせアクをとります。
(3)適当な量の砂糖を溶かし、塩をひとつまみ入れ、こげつかないように弱火でよくかき混ぜながら、お好みの濃さに調整してください。
※お酒の匂いが好みの方は、温めるだけでも良いでしょう。
☆酒蔵の冬の定番料理☆
【材料:4人分】
純米酒粕 120g
塩鮭の頭1個(ない場合はかつおだしでOK)
塩鮭の切り身
人参
大根
白菜
ネギ少々 など
【作り方】
(1)酒粕を細かくちぎって、一晩水につけます。
※一晩水につけるとお酒のにおいがぬけます
(2)鮭の頭を適当に切り、熱湯をかけて生臭さを抜いてから、水から煮てダシを取ります。
※ない場合はかつおだしで代用できます
(3)お好みの野菜(人参、大根、白菜など)を入れ、柔らかくなるまで煮ます。
(4)酒粕をお好みの分量煮汁で溶き入れ、少し煮立たせます。
(5)最後に鮭の身を一口大に切り、熱湯をかけてから鍋に入れます。 あまり煮過ぎますと味が抜けるので、さっと火を通すくらいで良いです。
(6)器に盛り付け、好みで刻みねぎなどをのせてお召し上がりください。
※粕汁は材料の酒粕と鮭の良し悪しが決めてです。
塩鮭は辛塩が合っているようです。あま塩の場合は塩を足します。
☆ご家庭でも魚の粕漬けがおいしくできます!☆
【材料:4人分】
純米酒粕 500g
ブリ 4切れ
赤味噌 100g
塩 小さじ1
【作り方】
(1)酒粕をレンジで柔らかくしてから味噌を加えて混ぜ、粕床をつくります。
(2)ブリをざるに並べ、両面に塩小さじ1杯を振って10分程度置いて水気をふきます。
(3)パットに(1)の半量をつめてガーゼを広げて(2)を並べ、上にガーゼをかけます。その上から残りの(1)をのせます。
(4)魚焼網を空焼きして油を塗り、魚の表を下にして載せます。弱めの中火で2〜3分焼いてから裏返してこんがりと焼きます。
※魚はブリの他、生鮭、タラ、サワラ、キンメダイ、タチウオなど、少し脂ののったものがよく合います。牛や豚の切り身や鶏モモ肉なども使えます。
【レンジで簡単!「粕床」の作り方】
一昔前は酒粕をちぎり、水をいれ、2〜3日おいてからすり鉢でのばしていましたが、今はもっと簡単です。
酒粕500gを耐熱性のポリ袋に入れ、レンジに約2分かけて上下を返し、さらに1分加熱します。袋の上から手でもんで十分柔らかくし、調味料を加えて混ぜ合わせます。
☆蔵元スタッフのレシピです!☆
【材料:4人分】
純米酒粕 250g
大根 800g
お湯 120cc
鮭(甘塩)2切れ
昆布茶 小さじ1
塩 少々
【作り方】
(1)酒粕は、お湯をかけてレンジで温めくずしておく。
(2)鮭は、焼いて骨と皮を除きほぐしておく。
(3)大根は、細めの拍子木に切り、鍋にぎゅっとつめる。その上に鮭をのせ、粕を全体に広げ入れる。
(4)ふたをして中火に約5分かける。大根の水分が少しでたら昆布茶をいれ、中火のまま混ぜながら火にかける。大根の食感をのこす程度までかき混ぜながら火にかけ、最後に塩を入れて味を調えます。
☆江戸時代より当家で代々伝わる秘伝の味です!☆
【材料】
純米酒粕
たまご
赤みそ
【作り方】
(1)一晩水でふやかした粕をぐつぐつ煮てアルコール分を飛ばす。
(2)お好みの分量のみそを入れ、さらに弱火で煮ます。
(3)最後に卵を溶き入れてできあがり。ご飯によく合い、冷めても美味しく召し上がれます。
※酒粕を使った料理をいろいろ試してみて、酒粕を気に入ったらぜひ試してみてください。
かなり強烈ですが、当家で江戸時代から代々伝わる伝統的な食べ方です。
他にもあさりの味噌汁に少量入れると生臭さが消えあさりの風味が生きてきます。お好みに合わせていろいろな料理法でお楽しみください。
こちらもどうぞ